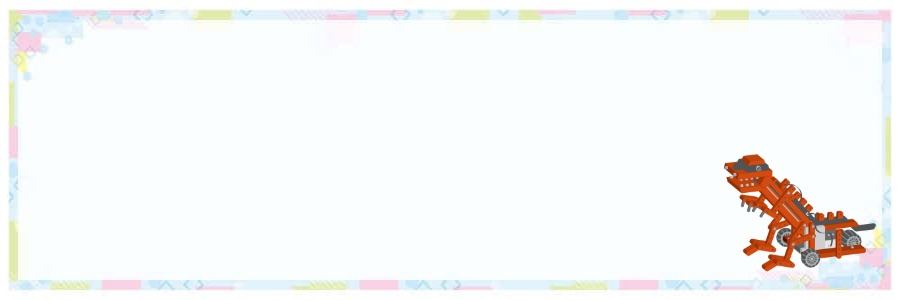もののしくみ研究室
学研が提供するロボットプログラミング教室です。
教材はアーテックのロボットを使用しているため、見た目はアーテックのロボットですが、授業のカリキュラムは学研が作成しているため中身は全く異なります。
学研が提供しているので学研の学習塾が多く取り入れています。
もののしくみ研究室の特徴
見た目はアーテックロボですが、ものの仕組み教室には特長があります。
身近にあるものを作るということです。
具体的にどんなものかというと自動ドア・踏切・信号機といったものになります。
実際に毎日見ているものを作ることで興味が湧くし、その仕組みを理解できるということになります。
作成したプログラムがうまく動かなくてもトライ&エラーで取り組めるようになっています。
しくみkids
ものの仕組み研究室は、パソコンを使用して行うことから小学校3年生以上が対象とされてきましたが、低学年向けのカリキュラムが登場しました。
アーテックと共同開発なので自考力キッズの位置づけなのでしょう。
2年間のカリキュラムとなっており4つのコースからなっています。
- カード式プログラミングカーコース
- テック&パズルコース
- ロボットプログラミング入門コース
- ロボットプログラミング問題解決コース
各コース60分となっており半年毎に進んで行くことになります。
ロボットプログラミング入門コースでは初めてパソコンを使うことになります。
「ものの仕組み研究室」と合わせると5年のカリキュラムになりました。
もののしくみ研究室の大会
現時点では学研が開催している大会はありません。
アーテックの教材を使用しているのでアーテックが開催している大会なら参加することができるでしょう。
アーテックの大会は、「URC2018」などがあります。
もののしくみ研究室のカリキュラム
3年間のカリキュラムとなっています。
エジソンアカデミーと同様に小学校3年生以上からとなっています。
Developer・Master・Innovatorというカリキュラムで段々と難しくなっていきます。
らせん構造のように学んだことを生かしながら新しいことを学んでいく仕組みになっています。
簡単に各コースの説明を行います。
Developer
最初の1年目ですのでプログラムの基本的なことを学びます。
身近な物の構造やセンサーを学びます。
Master
プログラミングは1年目よりさらに複雑になります。
複数のセンサーを使います。
自立型ロボットに挑戦します。
Innovator
変数を使ったさらに複雑なプログラミングを学びます。
デザインを意識した製品開発を行います。
もののしくみ研究室の料金
フランチャイズとして統一されているわけではなく教室によって異なります。
興味のある教室に問い合わせましょう。
アーテックロボの購入は必要となります。
京都のもののしくみ研究室の教室
ものの仕組み研究室はまだできて2年の教室なので教室数はそれほど多くはありません。
比較的京都市外に多いようです。
京都市
京都府
京都府の北部に教室があるのは珍しいです。
北部に住んでいる場合はあまり選択肢はないのでものの仕組み教室を考えてみてもいいでしょう。